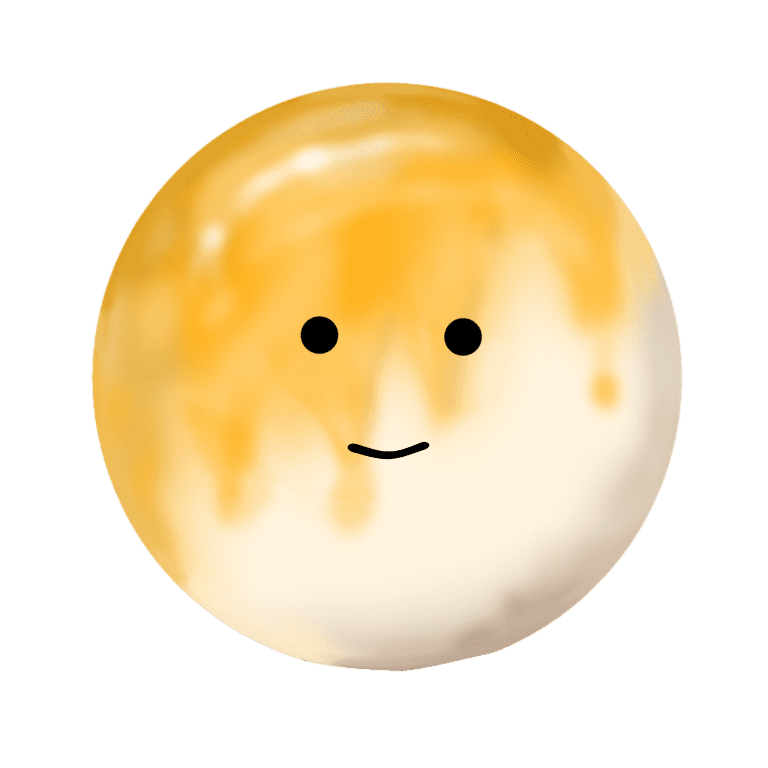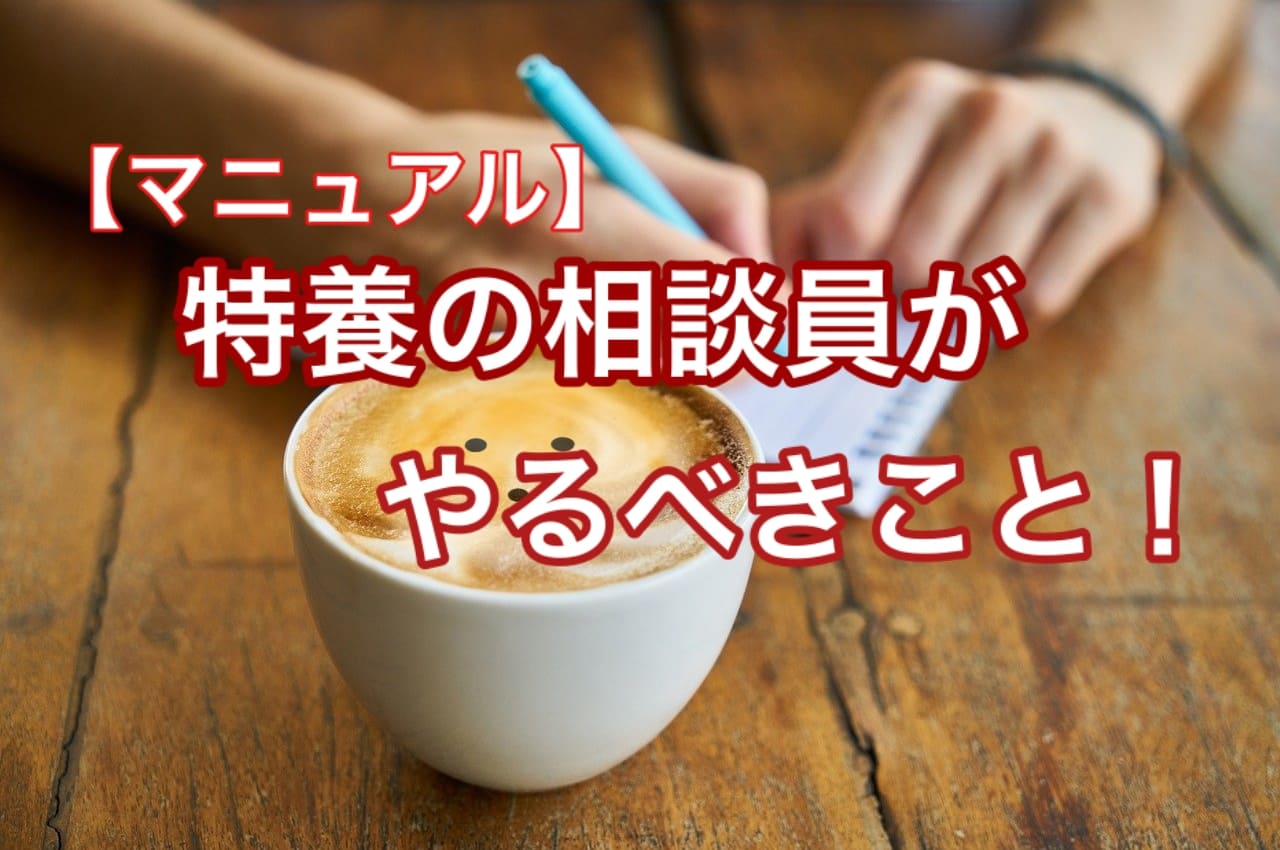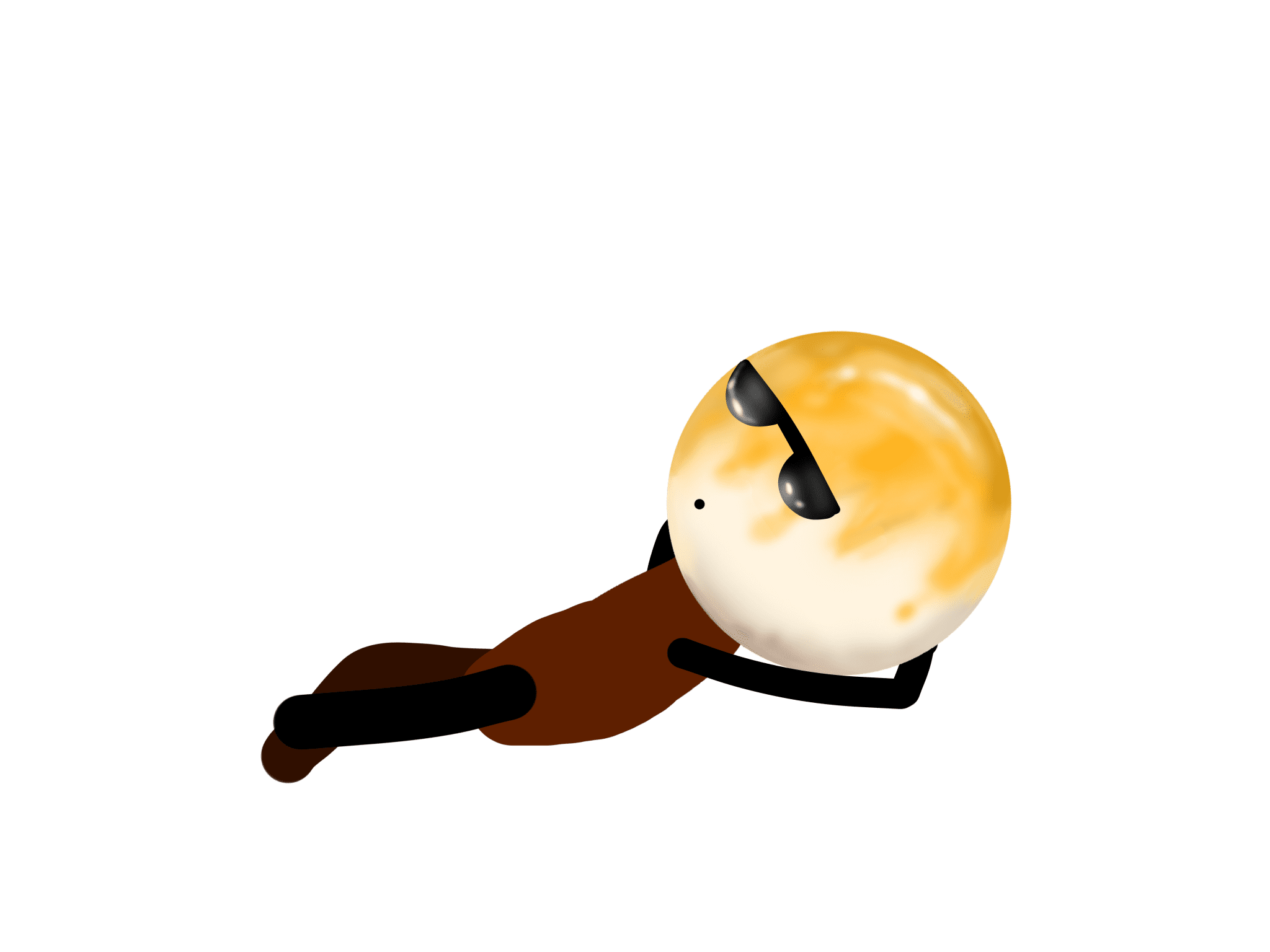こんな疑問をもっていませんか?
特養の相談員をやりたいけど、実際にどういう事をやるの?
他のサービスから特養の相談員に変わったけど、今までの仕事とどう違うの?
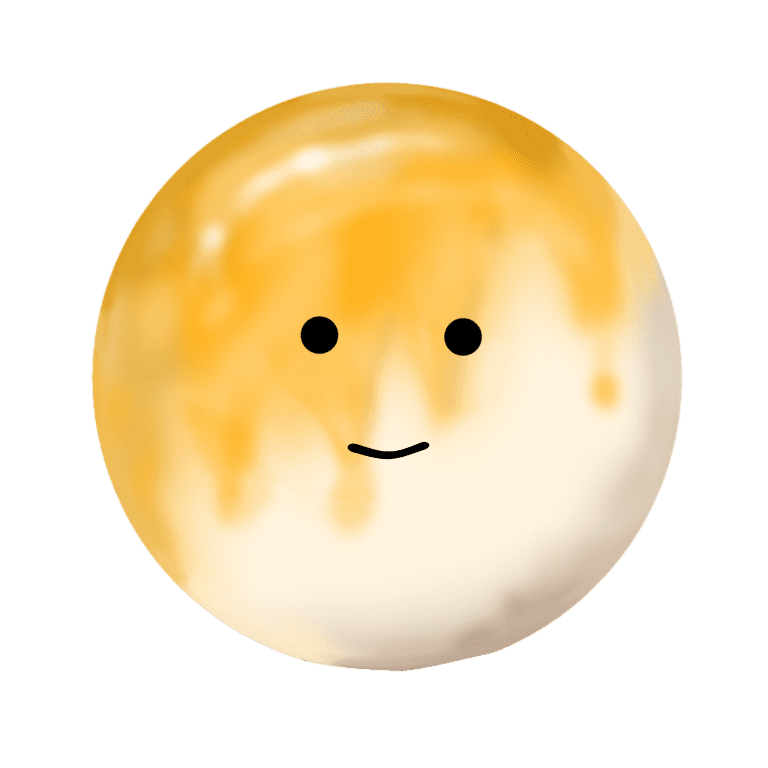
入居者さん100人規模の特養の中に、相談員は多くても3人程度。
つまりほぼ自分で考えて動いて行かないといけない業務という面が当然あります。
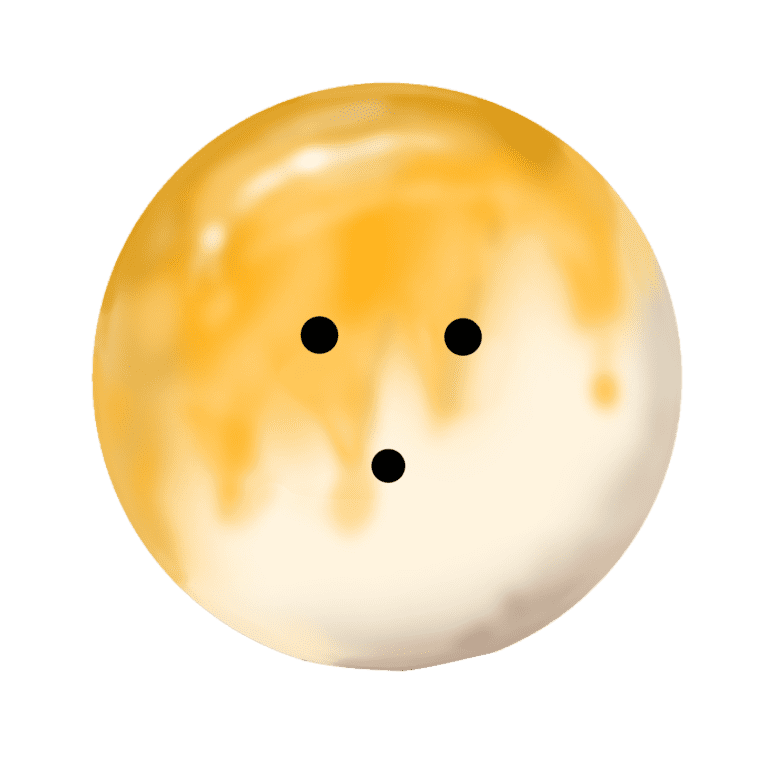
[toc]
特養の相談員が施設内部でやるべきこと!
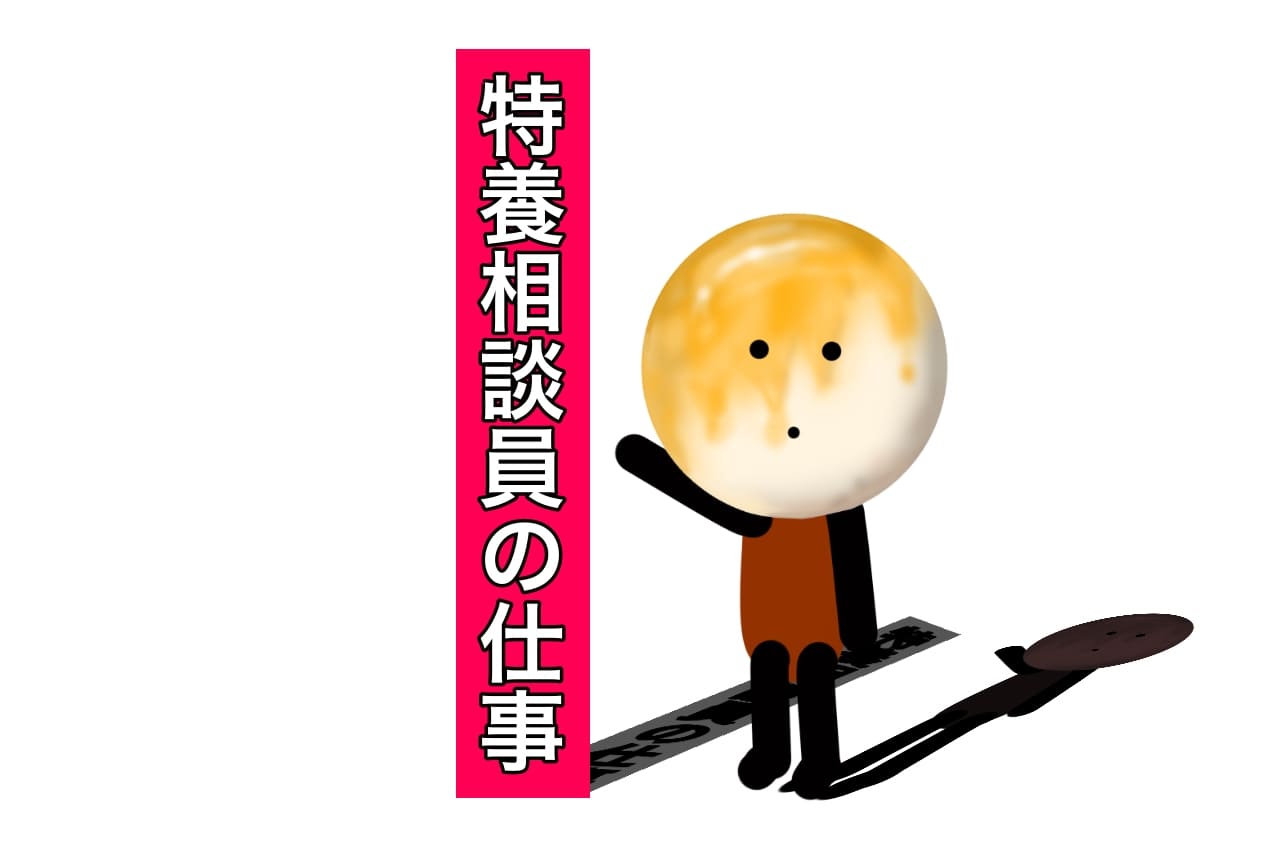
特養の相談員いなりたてや、別のサービスから特養に移った相談員さんは、施設内部でどのように動けばいいかをまず理解しましょう!
相談員の任されている仕事を理解する
相談員が特養で主に任されている業務は
- 入居者本人、入居者の家族、施設内の各部署、その他(社会資源等)の橋渡し役
- 入居者確保の為の営業活動
- 外部に対して、施設、特養というサービスなどの説明
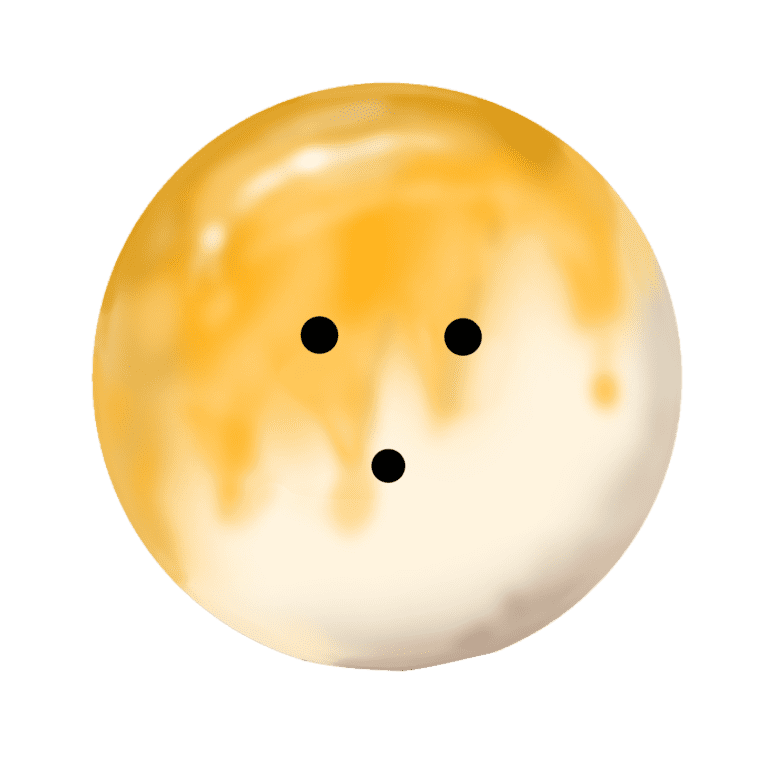
各部署、入居者サイドの間の橋渡しには、ケアマネージャーが行うカンファレンスの仲介や看護師からの医療的な意見の反映、ボランティアなど、社会資源を利用し手のサービス向上なども含まれます。
各部署の橋渡し
先ほどの項目と被りますが、
相談員はこんな人達の間を橋渡し
- 入居者本人
- 入居者の家族
- 施設の各部署(介護、看護、栄養、事務、管理 等々、、、)
これら個々の意見を、入居者さんの施設での生活がうまくいくように他部署への連絡、必要時の調整を行います。
仮に、各部署、家族などの意見がバラバラなら、それをまとめるのが主な業務です。
請求関係は理解しておくべき!
施設内の料金や、加算の算定根拠は、家族、介護士、看護士、栄養士などに説明できるようにしておかないといけません。
請求に関しては、事務員で行っている施設も多くあると思います。
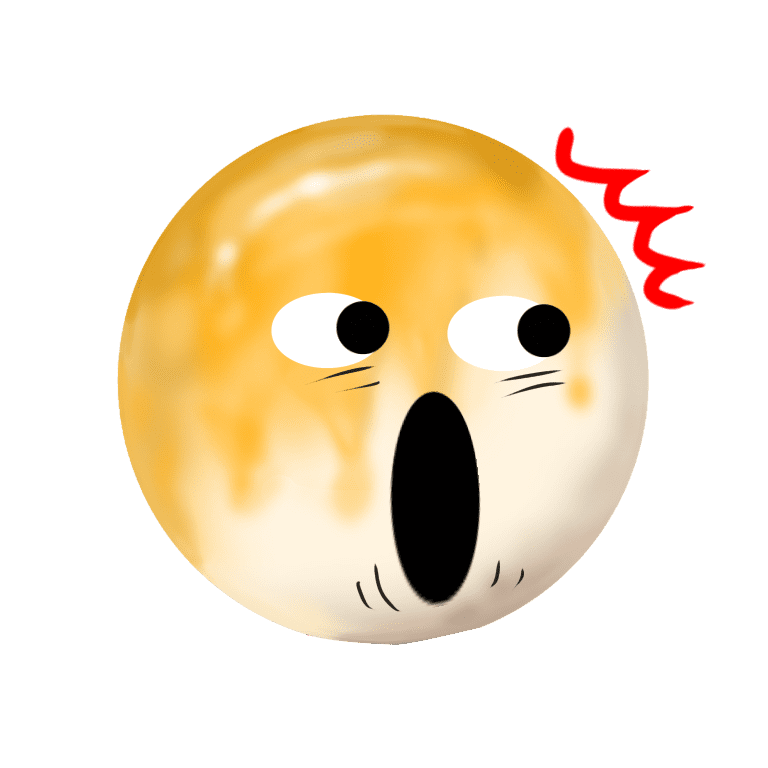
質問された時に答えられるようにはしておきましょう。
実地指導をクリアできるかが最低ライン
さきほどの、請求、加算項目はもちろん、身体拘束、入浴の回数、事故時の対応方法等、実地指導で確認される項目は最低限、頭に入れておき、普段からそのボーダーラインを各部署が下回ることがないように対応、助言していきましょう。
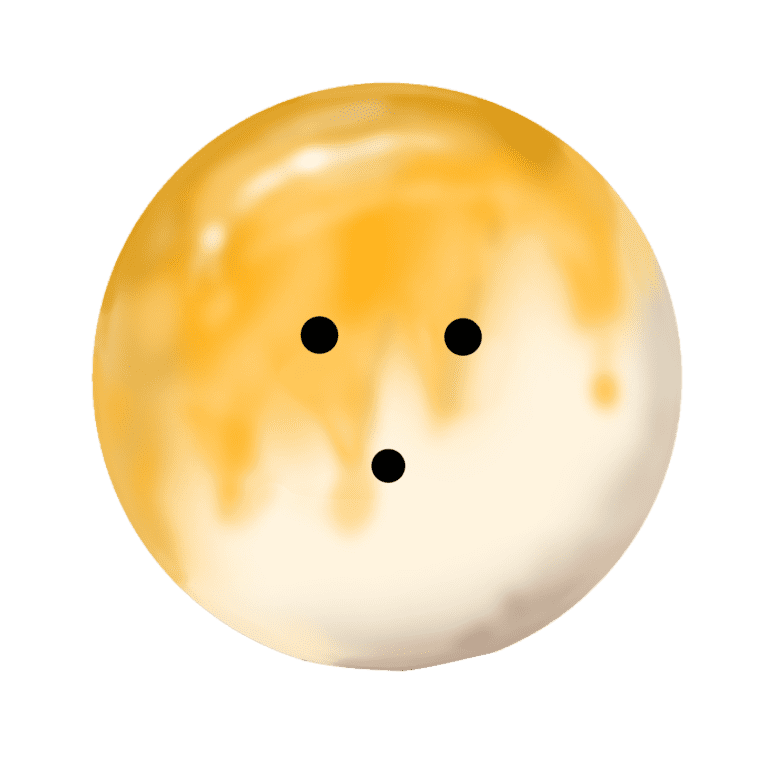
相談員になりたての方は、各都道府県、市町村が毎年提出を求めてくる、自主点検表を確認して、1項目ずつ回答してみてください!
他部署に向けてやることは?
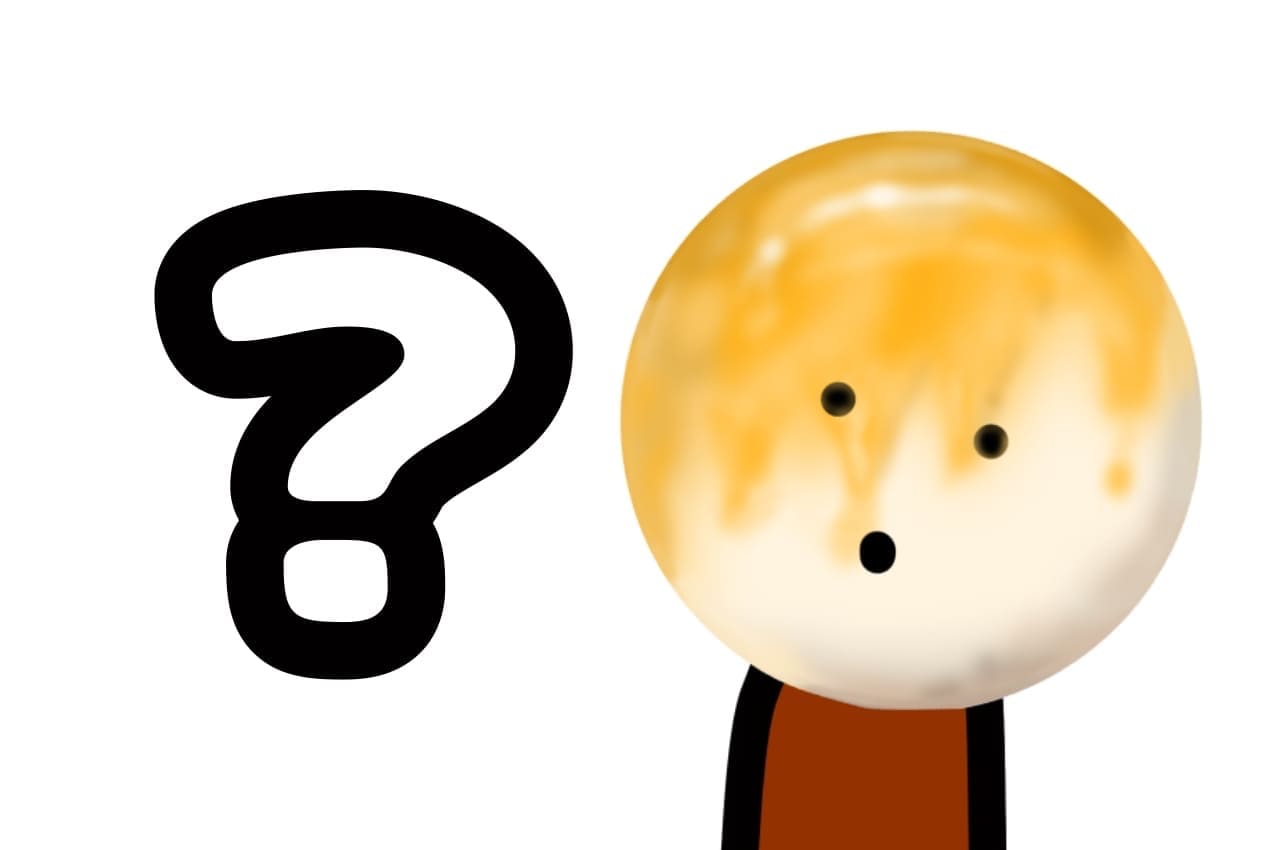
施設内で、多くの部署、関係者と関わる機会が一番多いのが相談員です。
ここでは、施設内の各部署に向けての特養相談員の動きを見て行きます。
家族からの意思を伝える
契約時の『重要事項説明書』にも記載されていることがほとんどだと思いますが、施設の相談窓口は相談員になっています。
家族からの希望、悩み、意見は相談員がまず聞く事になるので、それを各部署、適材適所に報告してたいおうしていきましょう。
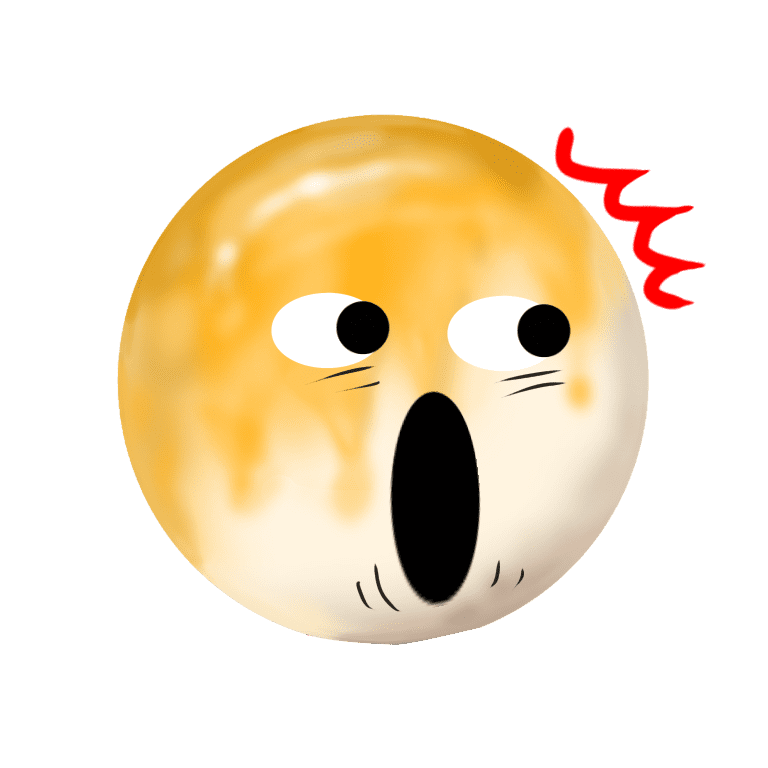
1人の入居者さんに対して、施設の意見のとりまとめ
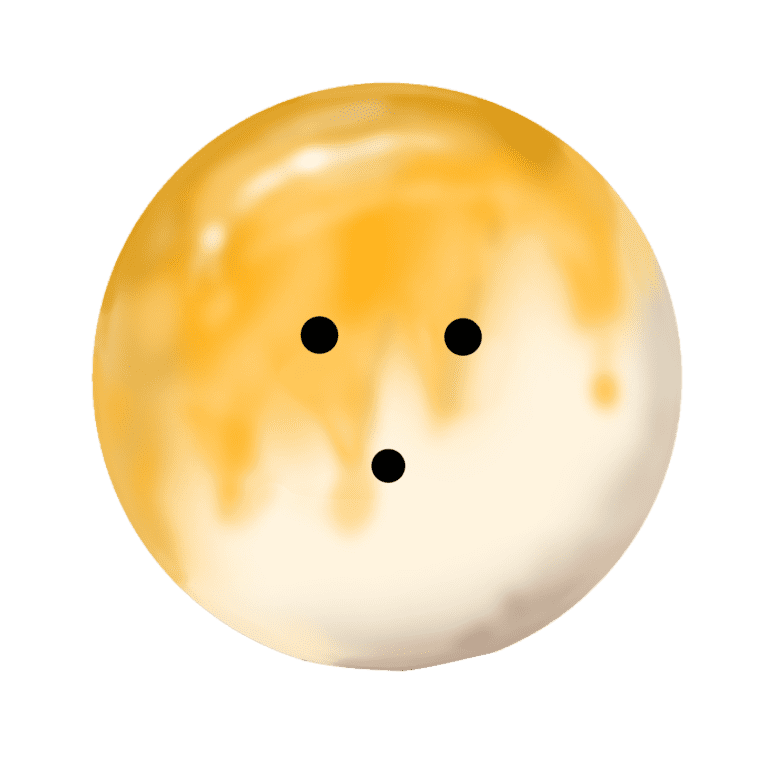
この場合、相談員もその中の一部にすぎないので、そこまで特殊な動きは必要ないでしょう。
しかし、1人の入居者さんに関しての話し合いをする際や、課題が発覚したさいは、相談員は各部署の真ん中で意見をまとめながら、良い方向に持って行かないといけません。
自分が良い方向に向かったかどうかは、誰にもわからないと思いますが、とにかく、その時その時で、周りの意見、施設の考え、介護保険のルール等を把握しながら全力で対応して行く必要があります。
施設、法人の考えからズレない為の調整
施設、法人の考え方と、介護士、看護士の考えがズレてしまう事がよくあります。
よくあるのが
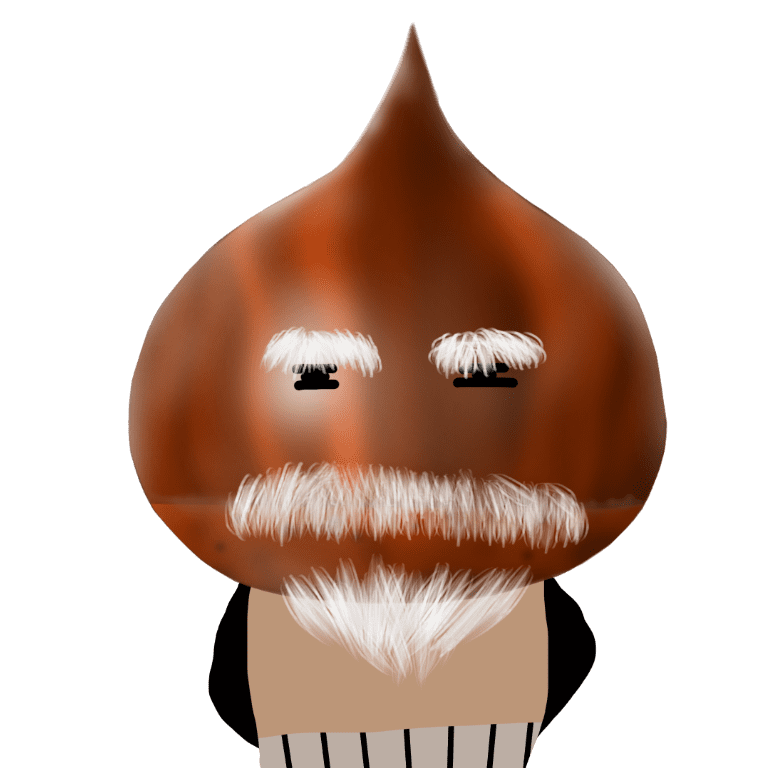
という法人の全体の決まり、考え方があるのに、
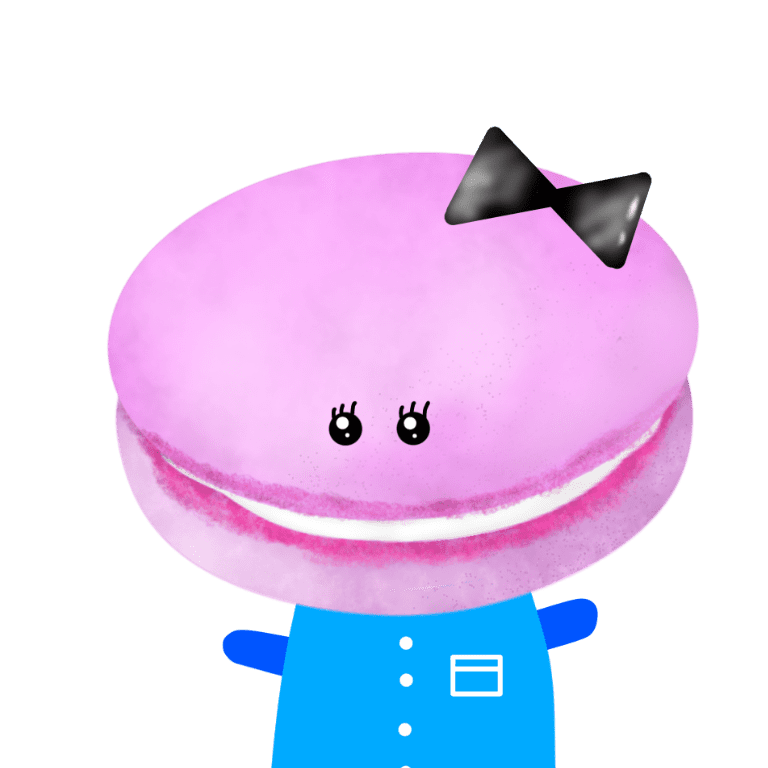
こんな感じで、向いている向きが噛み合ない事があります。
管理者に対応してもらうというのも、当然の考えですが、まずは相談員が法人、施設の考えは理解しておいて、そこがズレてしまっていたら、しっかりと訂正しましょう。
他部署より偉くならないように注意!
相談員になったから、他部署は自分の部下!
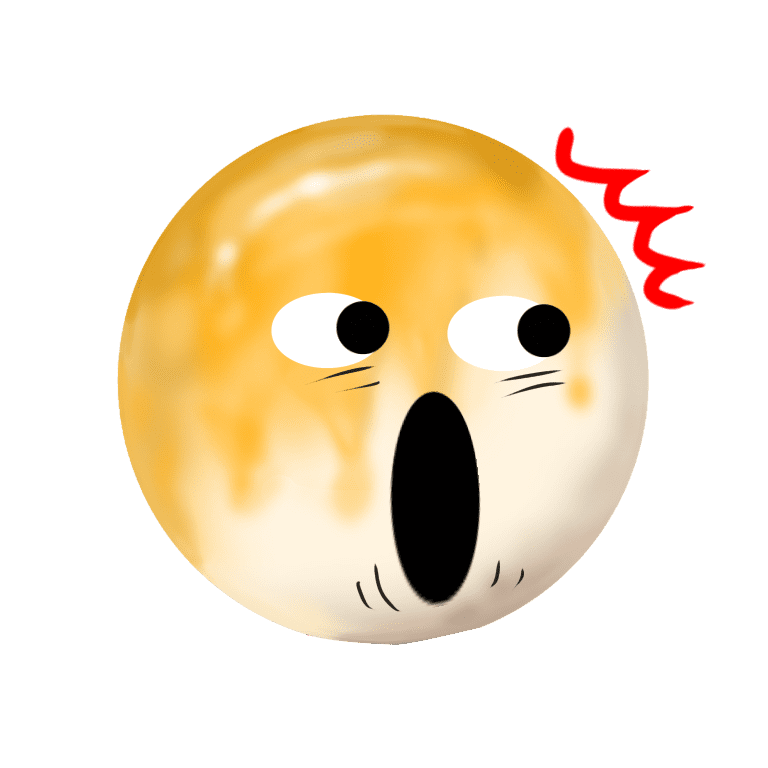
もし、こう考えているなら改めてください!
相談員は必ずしも上司ではない
上司かどうかは、各施設で組織図があるはずです。
その組織図で上に配置されているなら、会社員として上司ですが、相談員は必ず上司というのはおかしい考え方です!
相談員が色々な人に指示をださないと行けないのは、自分に家族や他の部署からの要望が集まっているからです!
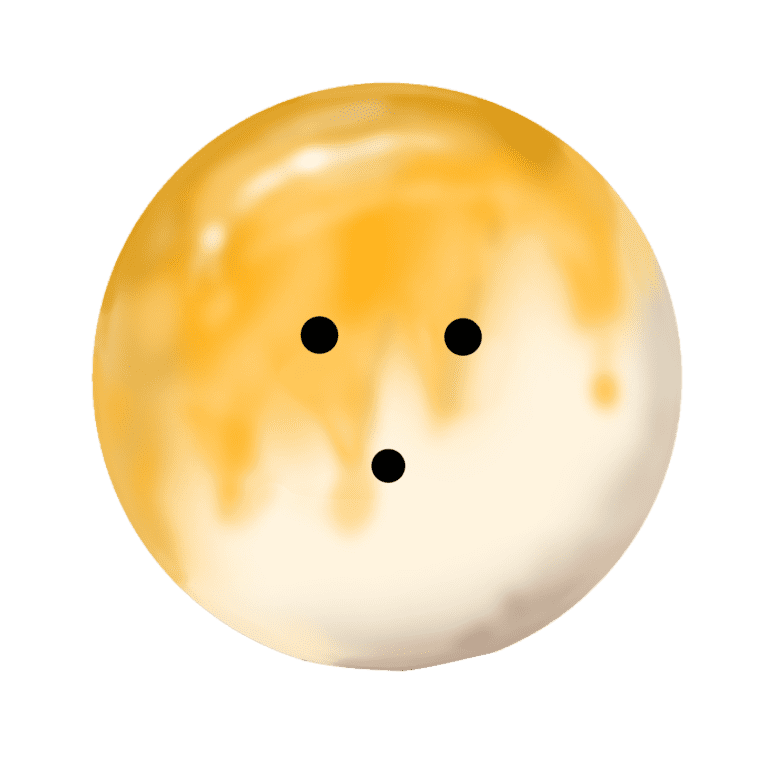
ではない事を理解しておきましょう!
気に入られたくて意見を言わないのはアウト
ただし、介護士や看護士などに気に入られたくて意見を言わない相談員はアウトだと考えて良いでしょう。
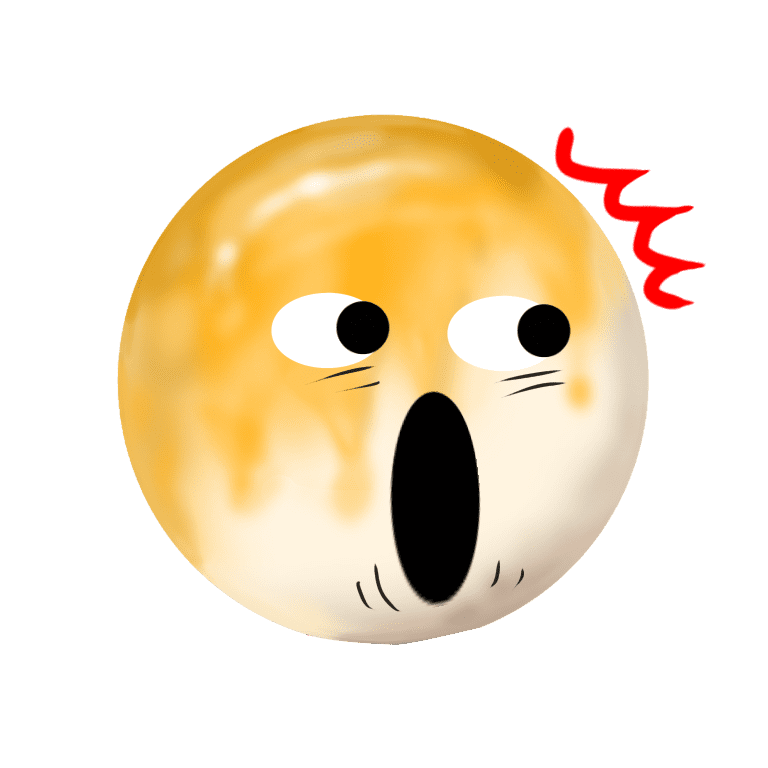
家族が希望しているサービスで、あまりにも無茶な事を言っていなければ、少し戦ってでもサービス向上の為に意見を言わなくてはいけない場面も当然出てきますよ!
各部署に主任やリーダーがいる!無視して突っ走らない
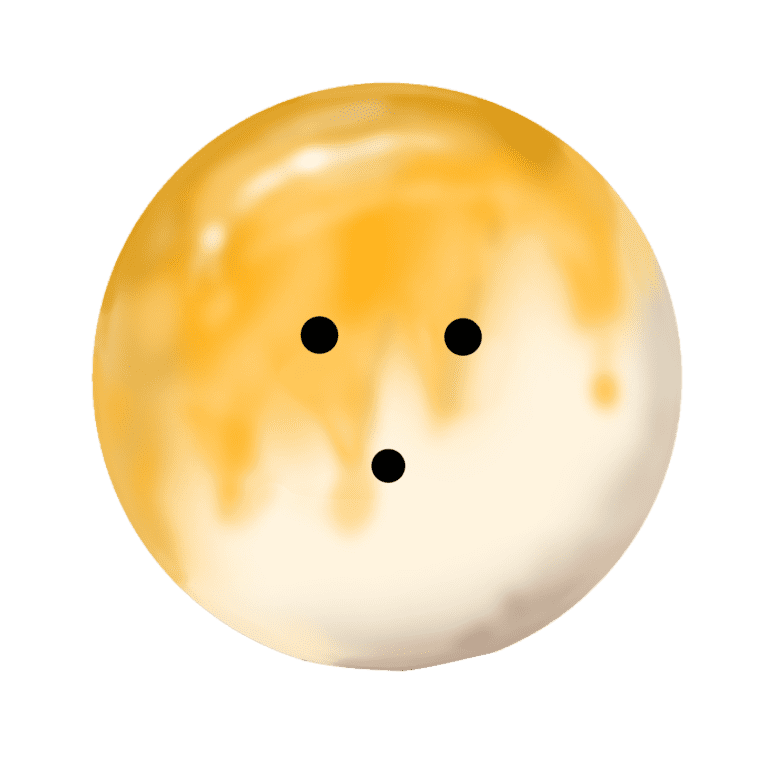
例えば、言葉遣いなど、その場で一時的な指導することはしなくてはいけませんが、必ず、その部署の主任などに話を通しておきましょう。
主任やリーダーも無視して、相談員が全てやろうとしていると、組織が崩壊します!
特養とはいえ、あくまでも会社です!
組織図をしっかりと理解して動きましょう。
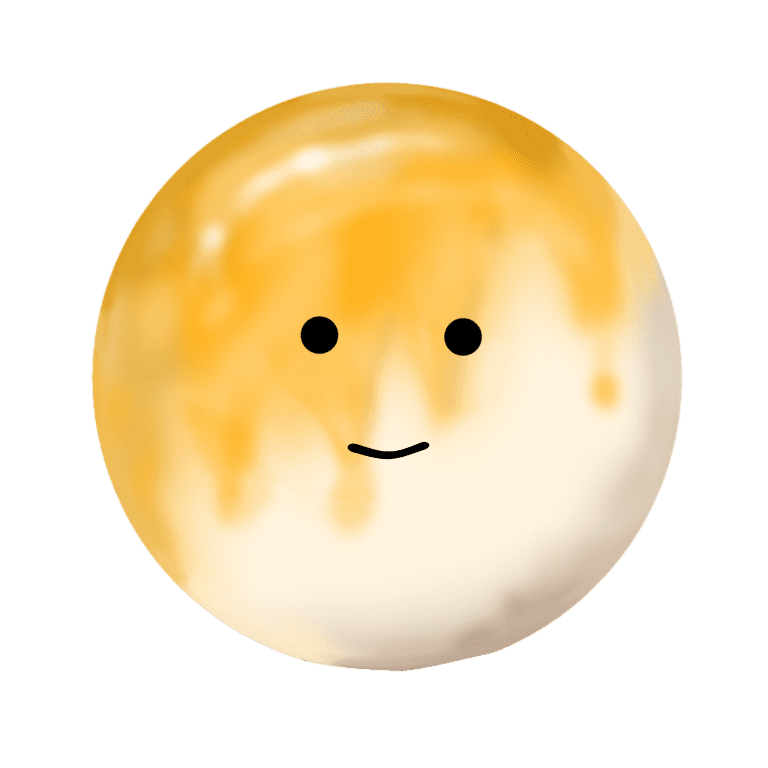
入居者の受け入れ基準に関しては、施設で決めた基準を下回らないように対応!
他部署より偉くなった気にならない!というのを勘違いして、入所の基準も介護士や看護士の意見だけで決めてしまうと、そのメンバーによっては施設の考えから大幅にズレます!
例えば、認知症の症状が強い人の申し込みがあった際に、介護士が
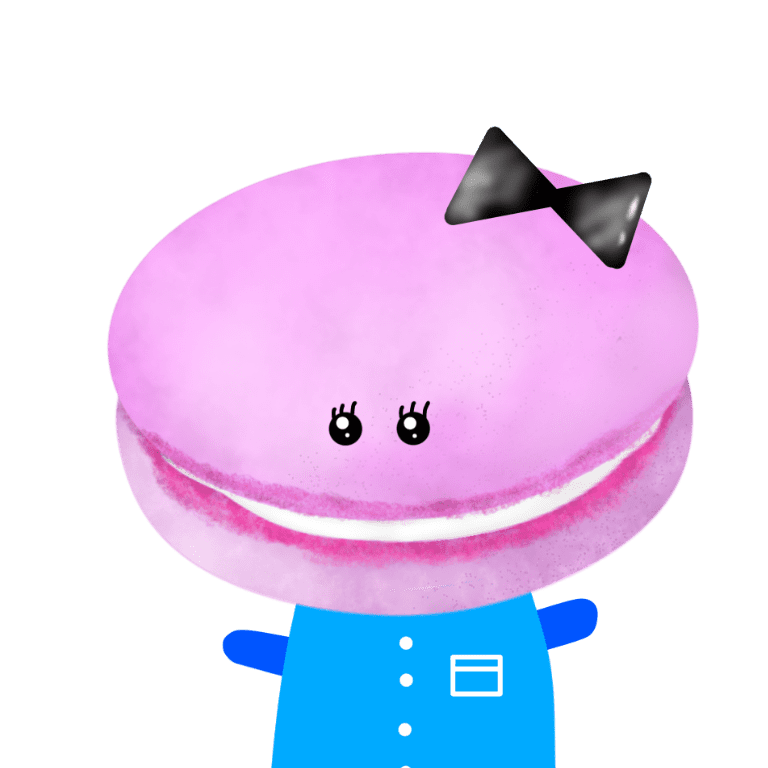
と考えたとします。
いくら、相談員が上司ではないとはいえ、この方向性を修正するのは相談員の仕事です!
特養の相談員が家族に向けてやるべきこと!
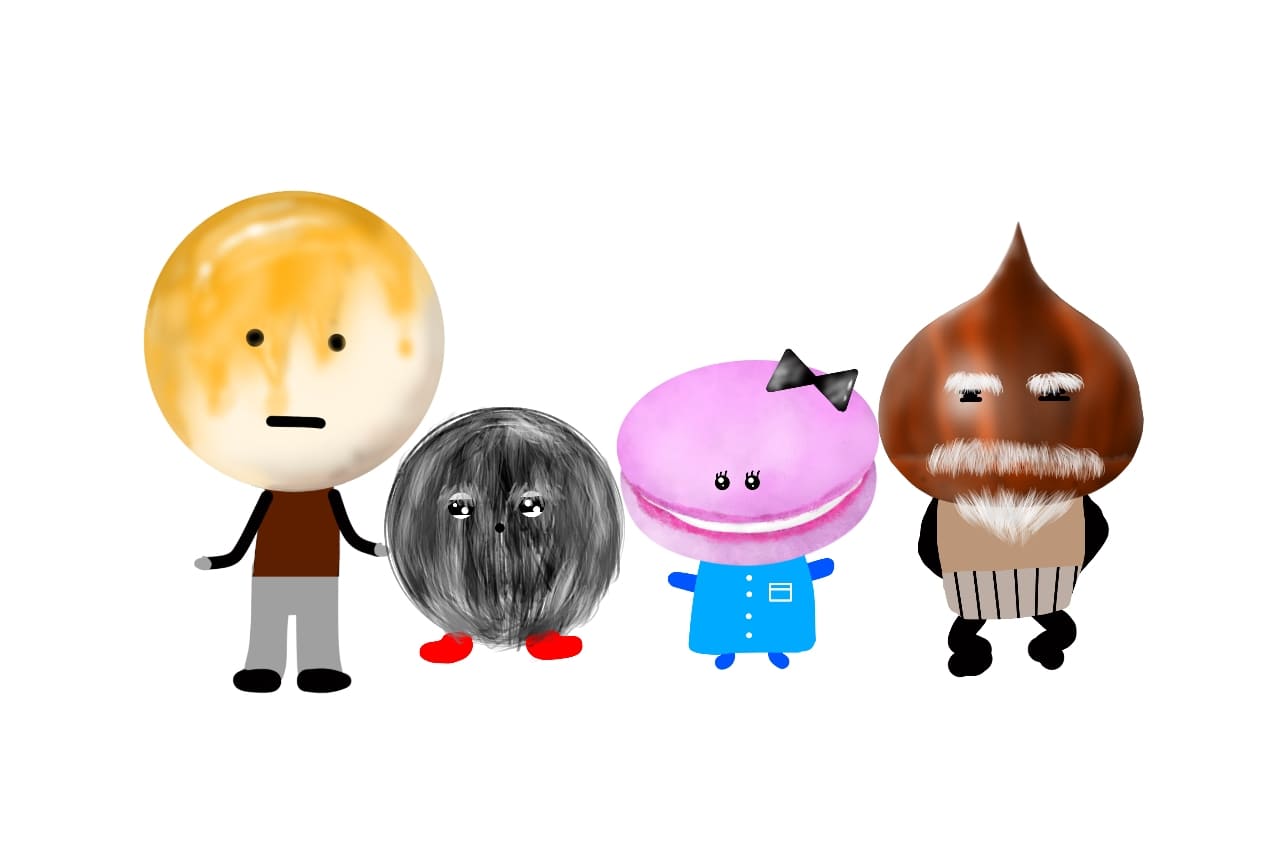
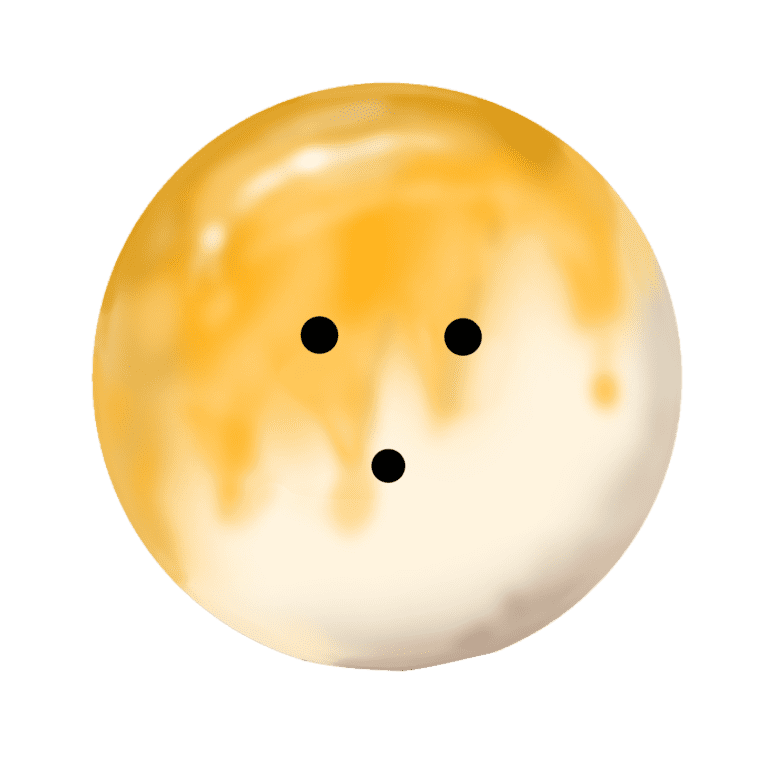
家族との連絡、関係作りは、入居者さん、家族の為だけではなく、施設の為にもなります!
状態の報告
状態の変化があった際や、事故があった際の連絡は言うまでもありませんが、適時、家族へ伝えましょう。
- 転倒するたびに連絡が欲しい家族
- 怪我した時だけの連絡でいい家族
- 救急車を呼んだり、入院の時だけでいいという家族
連絡の頻度は家族によって違います。
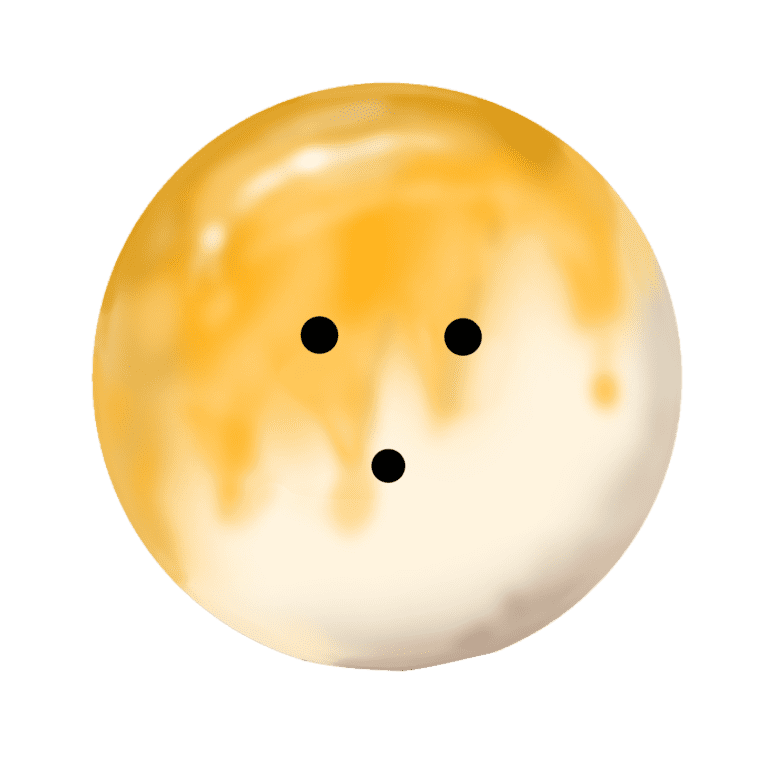
状態の報告は事故だけじゃない!事前のリスク報告も忘れずに!
事故以外の報告もしよう!
- 最近、歩行状態が悪くなって来た
- 食欲が下がって来た
- 認知症が進行したように思える行動が増えて来た
こんな時も、家族が忙しくなさそうな時間を見計らって連絡しておきましょう。
面会に来た時でもいいのですが、もし相談員不在の時に面会に来て、

となった時に、不信感にも繋がりかねません。
家族が内部の事を聞きやすい関係を作る!
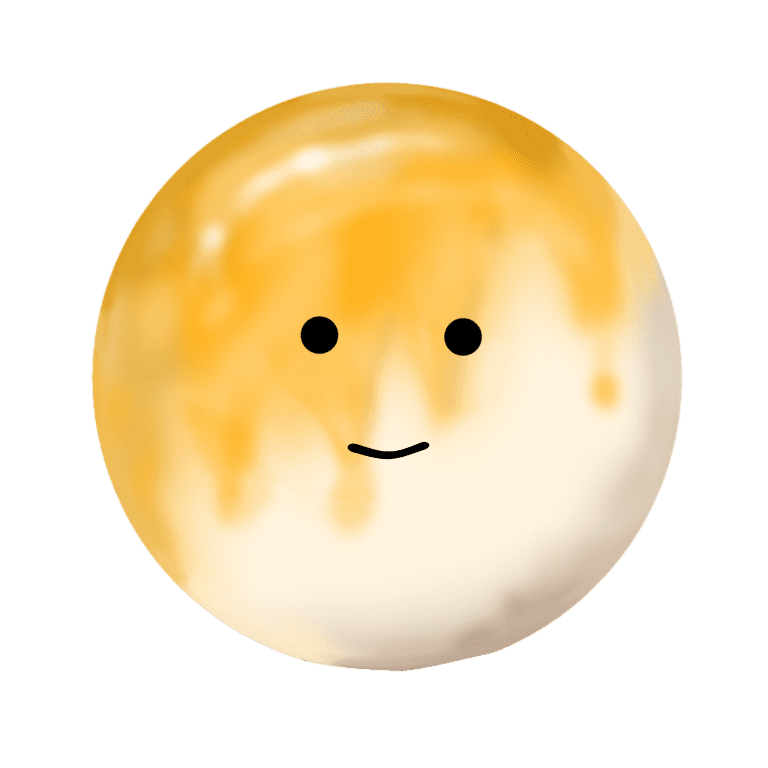
普段から、家族がくだらない事でも相談員に質問できたり、雑談できたりする環境を作れるのがベストです。
家族が相談員から内部の事を聞いて、イメージできるのと、何もわからないままなのでは、何かあった時に、

という不信感が出て来てしまうかもしれません。
相談員も完全に施設の人だから、遠慮して話せないのはNG!
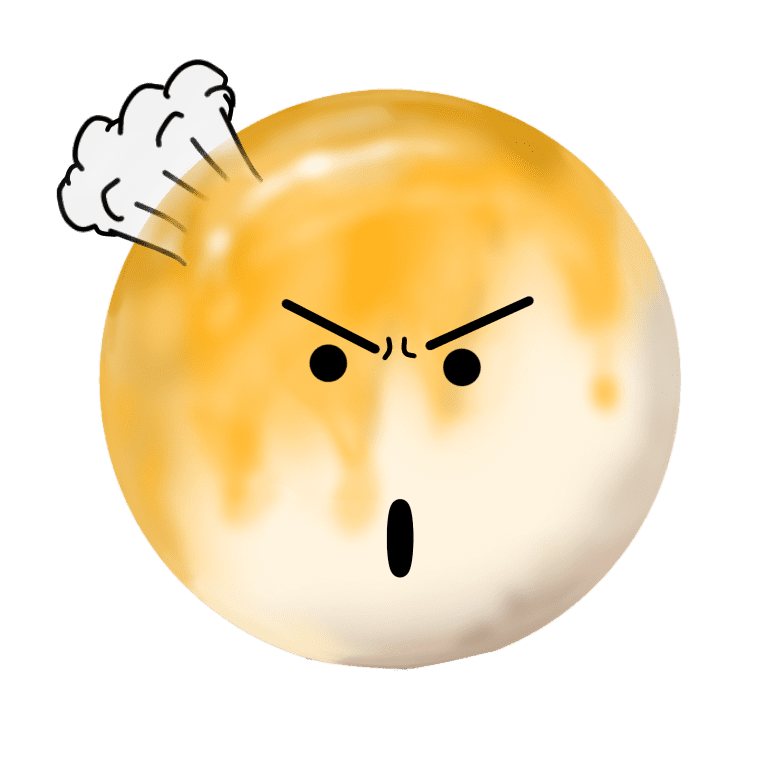
こう思わせてしまったら、関係を築くのはかなり難しくなってしまいます。
契約前、できれば見学の時から、

このように思わせないといけません。
施設と家族の間の人というイメージ、ポジションのみせ方が大事です!
関係構築はリスク回避の為の一番の対応策!
入居者さん、家族との関係構築は、

っということだけではありません。
家族との関係を構築する事で、不信感を取り除ければ、施設での活動の理解や、防ぎようのなかった事故の際等も、理解してもらえるようになりやすいのです。
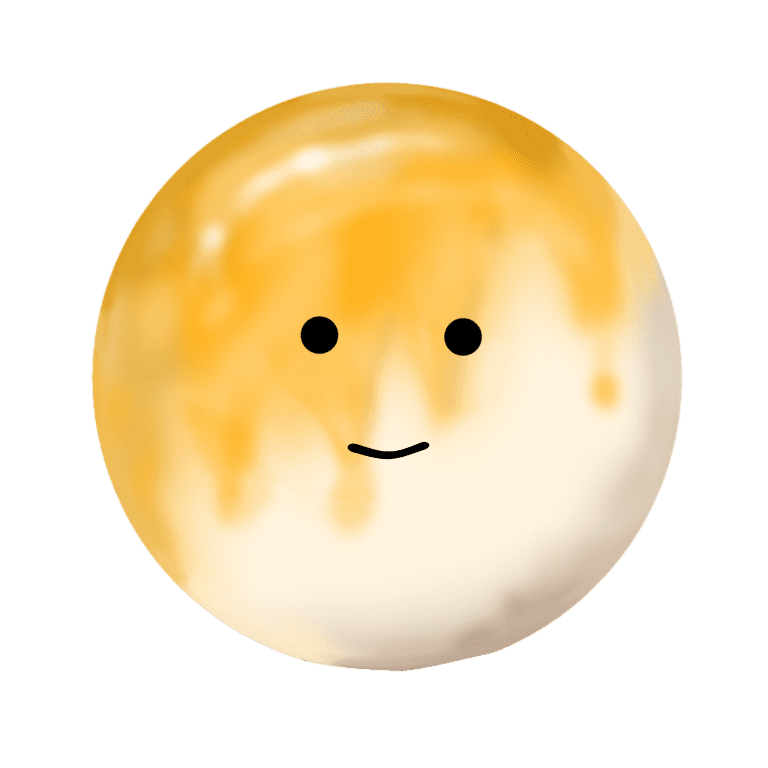
特養の相談員が営業の為にやるべきこと!
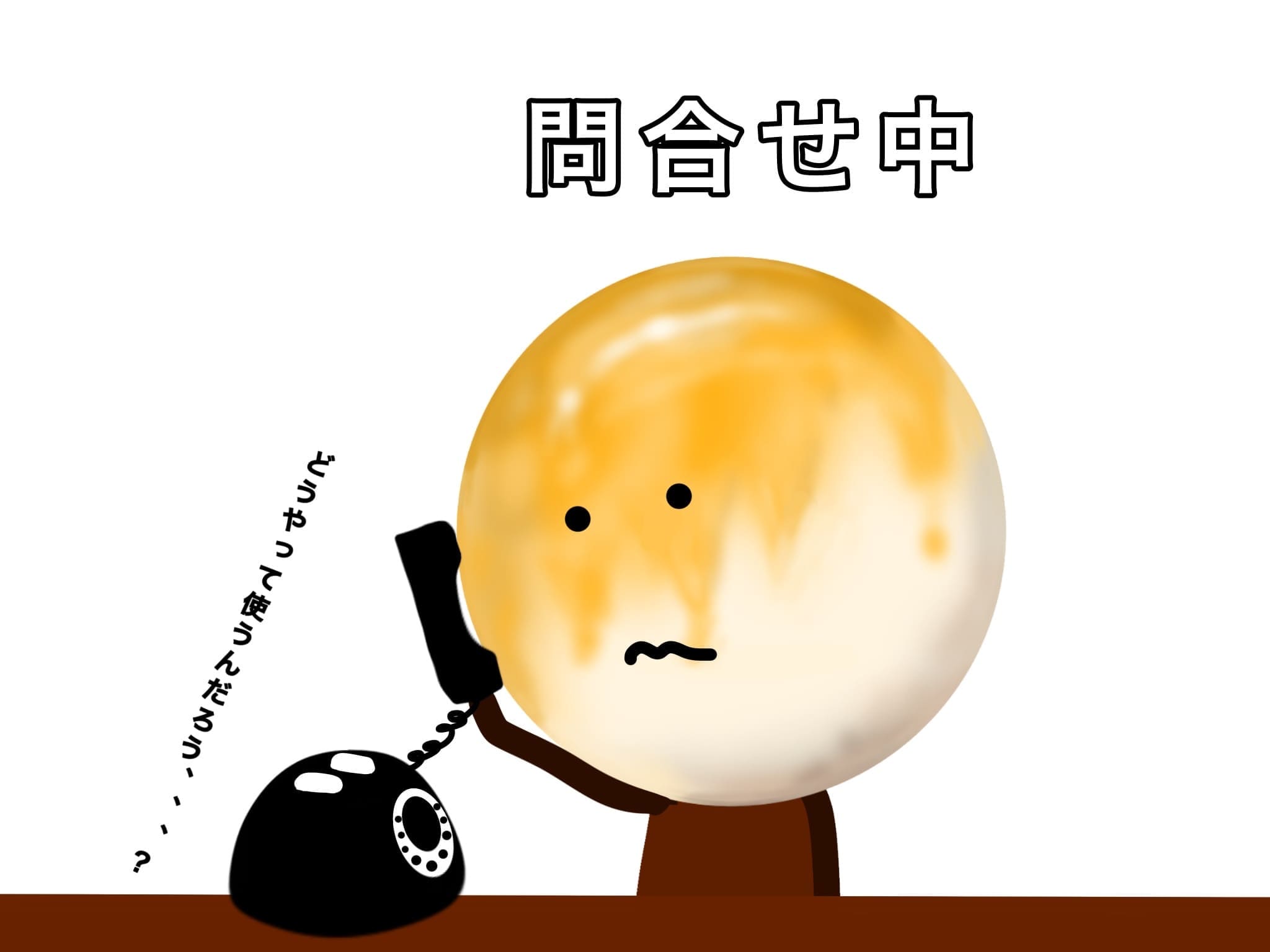
特養の相談員は、営業の面も任されている事がほとんどです。
待機者の確保
今は、以前のように特養の待機者は溢れかえっているという訳ではなく、待機者が少なくて、特養側から探しにいかないといけないという地域も少なくありません。
ショートステイと併設の事業所であれば尚更です。
営業に関して、有料老人ホームでは、営業専門のスタッフがいたりしますが、特養では主に相談員が担当する事になります。
居宅(ケアマネージャー)、病院への営業活動
特養の営業先はこんな所
- 居宅介護支援事業所のケアマネージャー
- 病院
この2カ所です。
病院によっては、あらかじめ、ソーシャルワーカーと会うのに予約が必要な病院もあるので、できれば1本連絡を入れてから向かいましょう。
営業時は「今、うちの施設はここがすごい!」を用意!
営業に行って
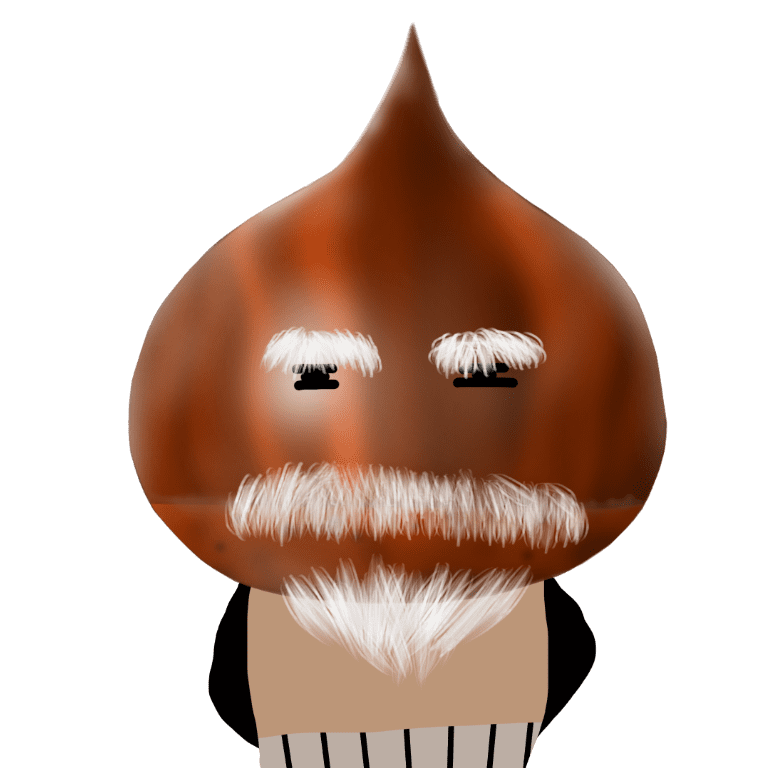
と聞かれた時に、
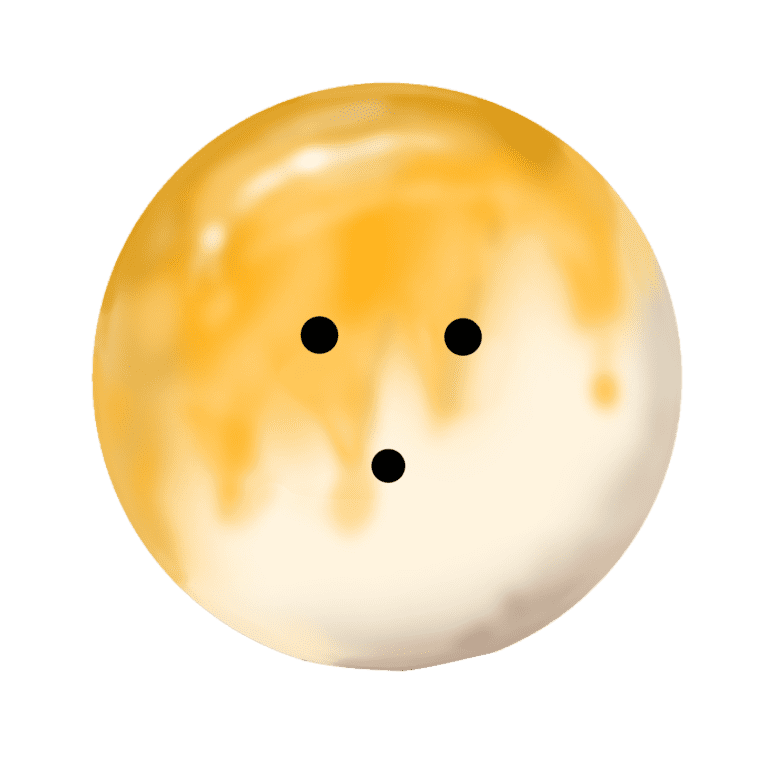
これでは、印象にも残りません。
例えば、大げさな例ですが
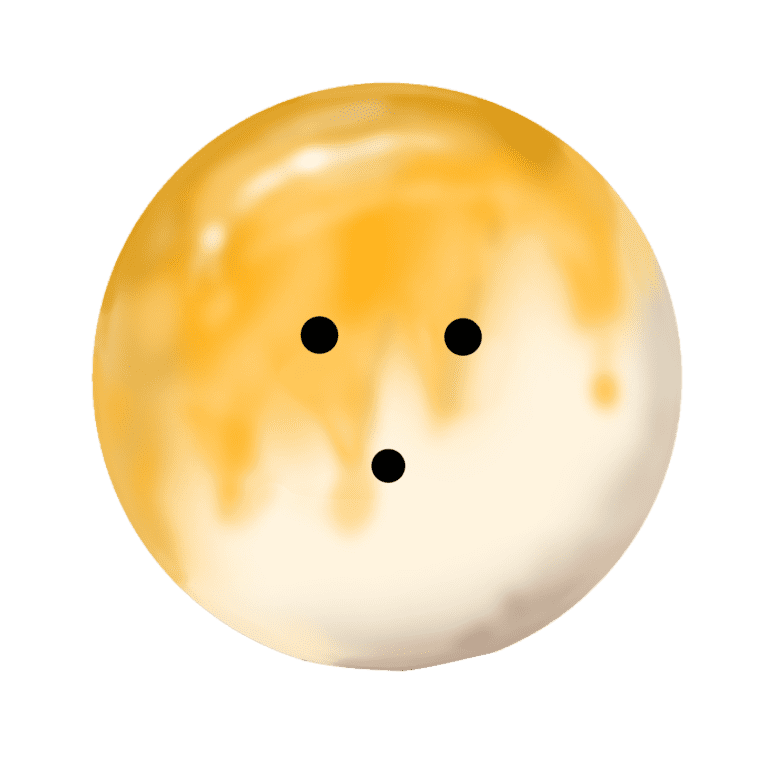
といったように、他より、ここの面ではすごいですよ!というアピールをできるようにしておきましょう。
見学のシュミレーションは必須!
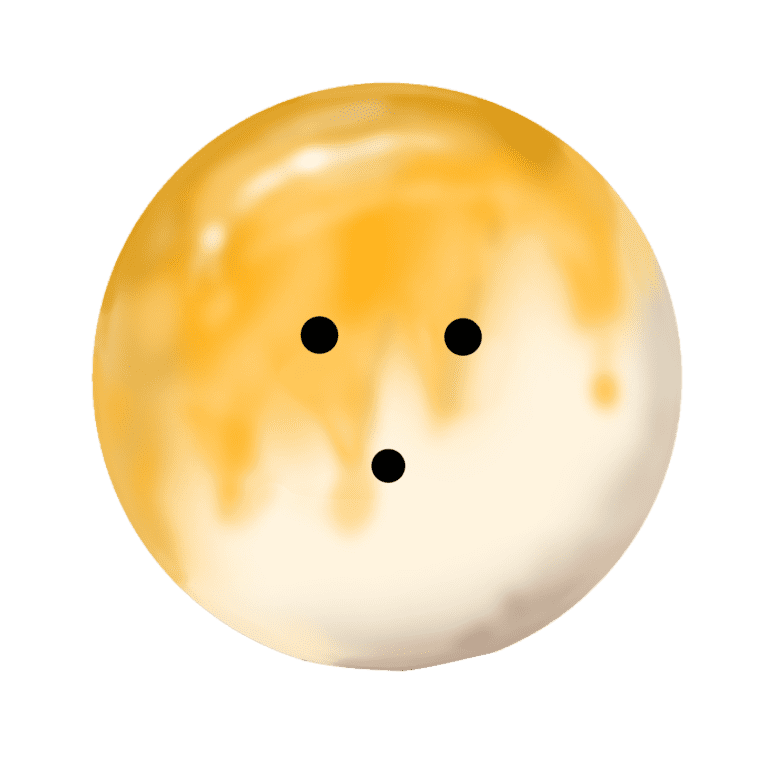
その際に効果的なのが、見学対応時のシュミレーションです!
見学といっても、施設内の全部屋をみせる訳でもありません。
だいたいの場合が、相談員が案内しながら、見学者はついてくるというスタイルです。
見学前にこんな事を考えておく!
- この時間に日当りがいい部屋はどこか
- 特徴ある設備を見せる
- 部屋の雰囲気は◯◯さんの居室がいいから見学の許可を取っておく!
こんな感じで、ある程度の流れを作っておきましょう。
特養の相談員は必ずしも明るくなくても大丈夫!でも不機嫌はNG!
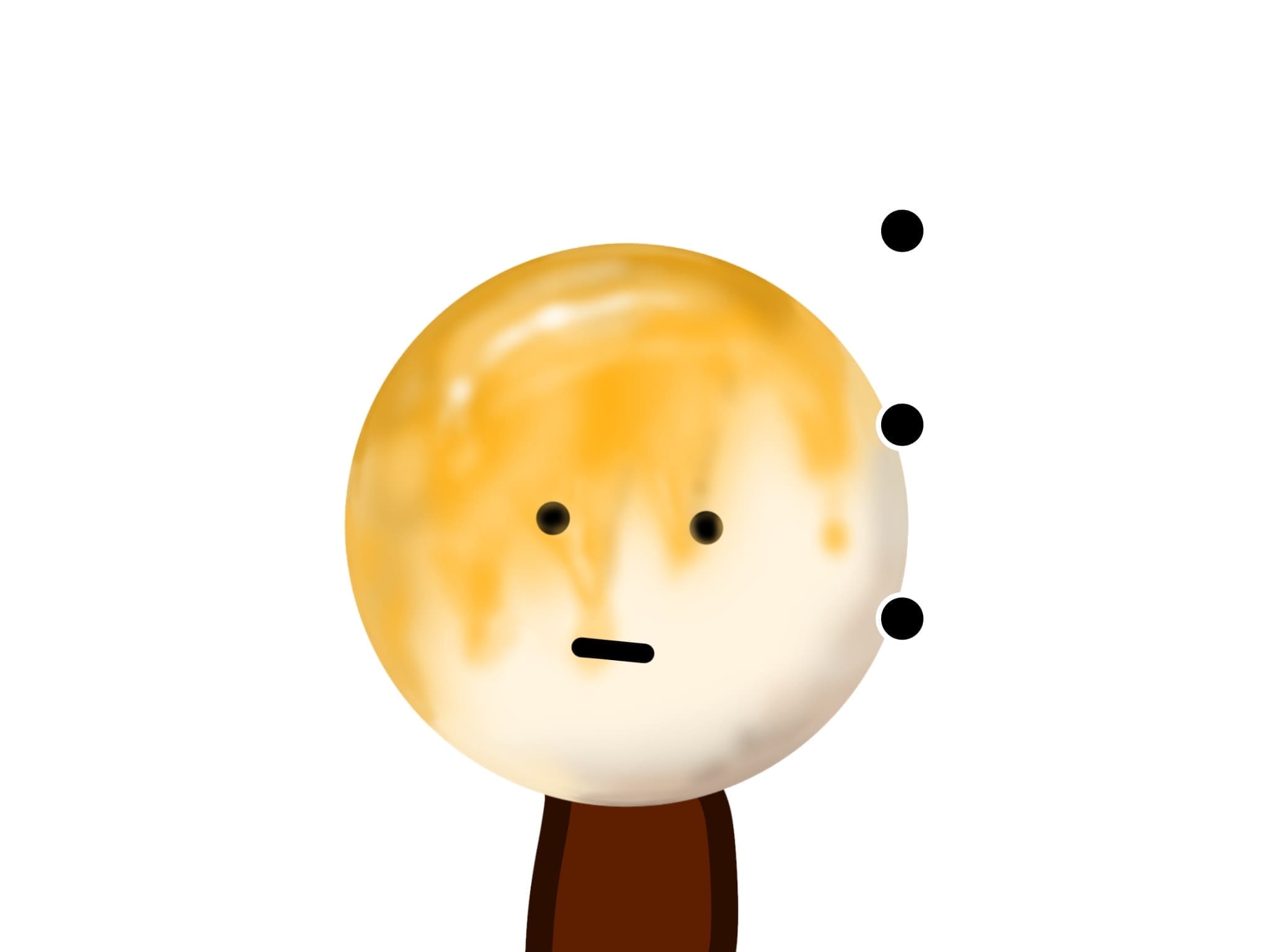
施設ごとの考え方によりますが、私が色々な相談員と関わって来てすごく感じるのが、
明るい=良い相談員
では無いということです。
大人しい人でも、家族との会話のアタリが柔らかかったり、何かがあった時の動きが早かったりと、相談員に向いている人はたくさんいます。
明るい人は明るい人なりの、大人しい人は、大人しいなりの相談員業務のやり方があるので、もし
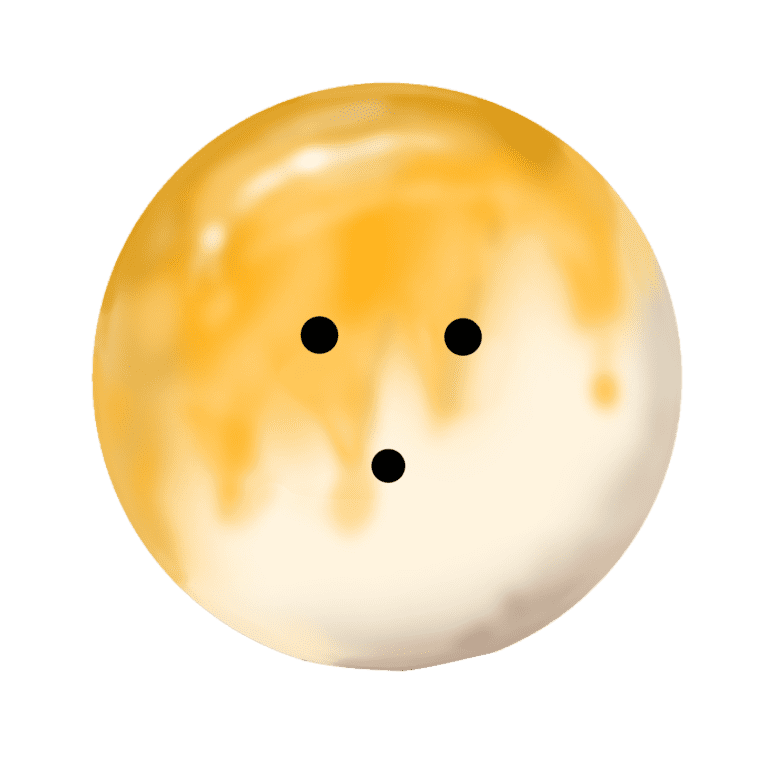
と考えている人がいたら、あまり気にせずに、やりたいという意思を管理者等に伝えておきましょう。
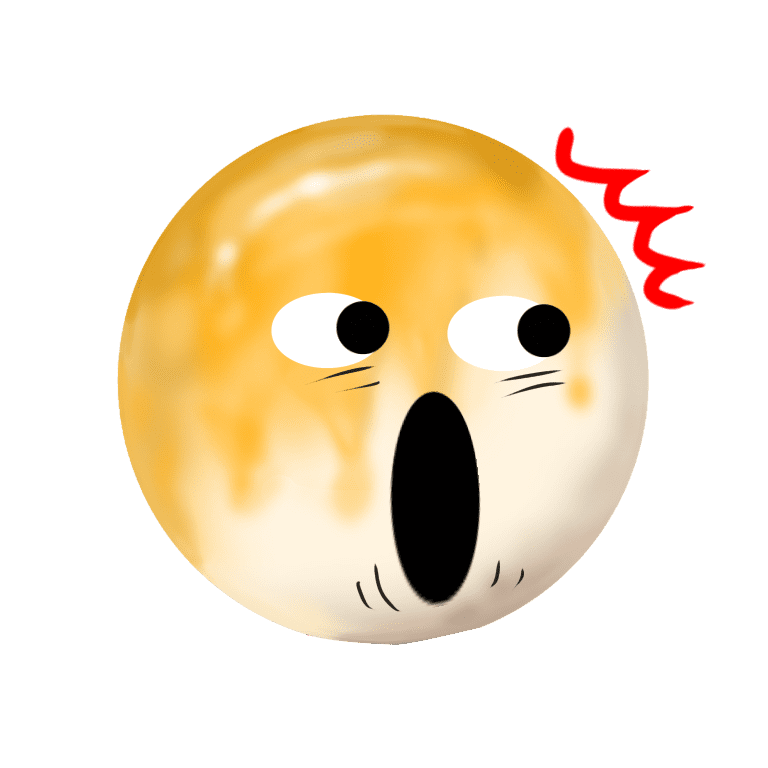
明るくても暗くても、電話や面会時、契約時などに、相手に対して

と思わせるのはNGです!
明るかろうが、大人しかろうが、相手に対して感じよくすることは必須です。
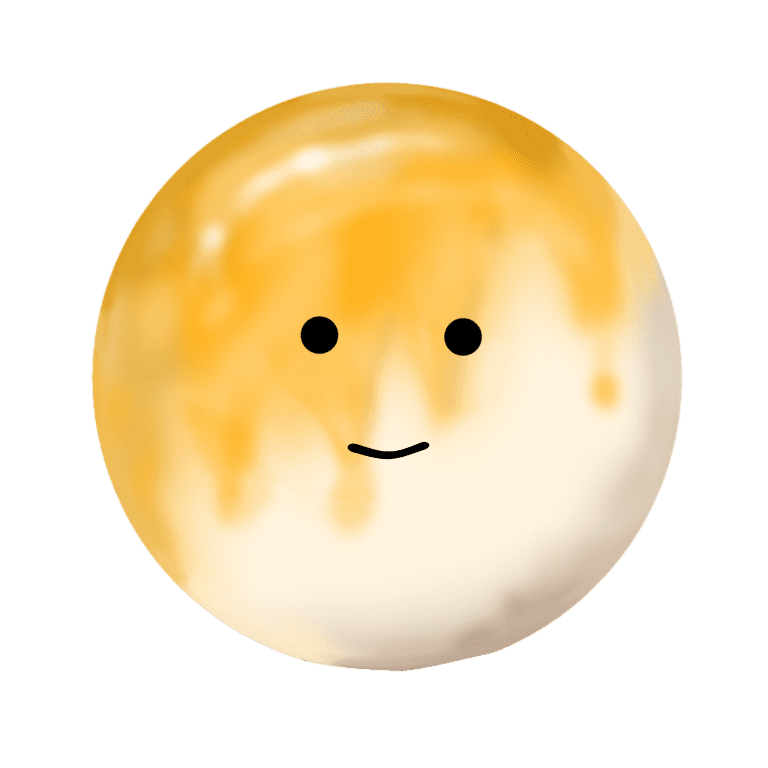
-
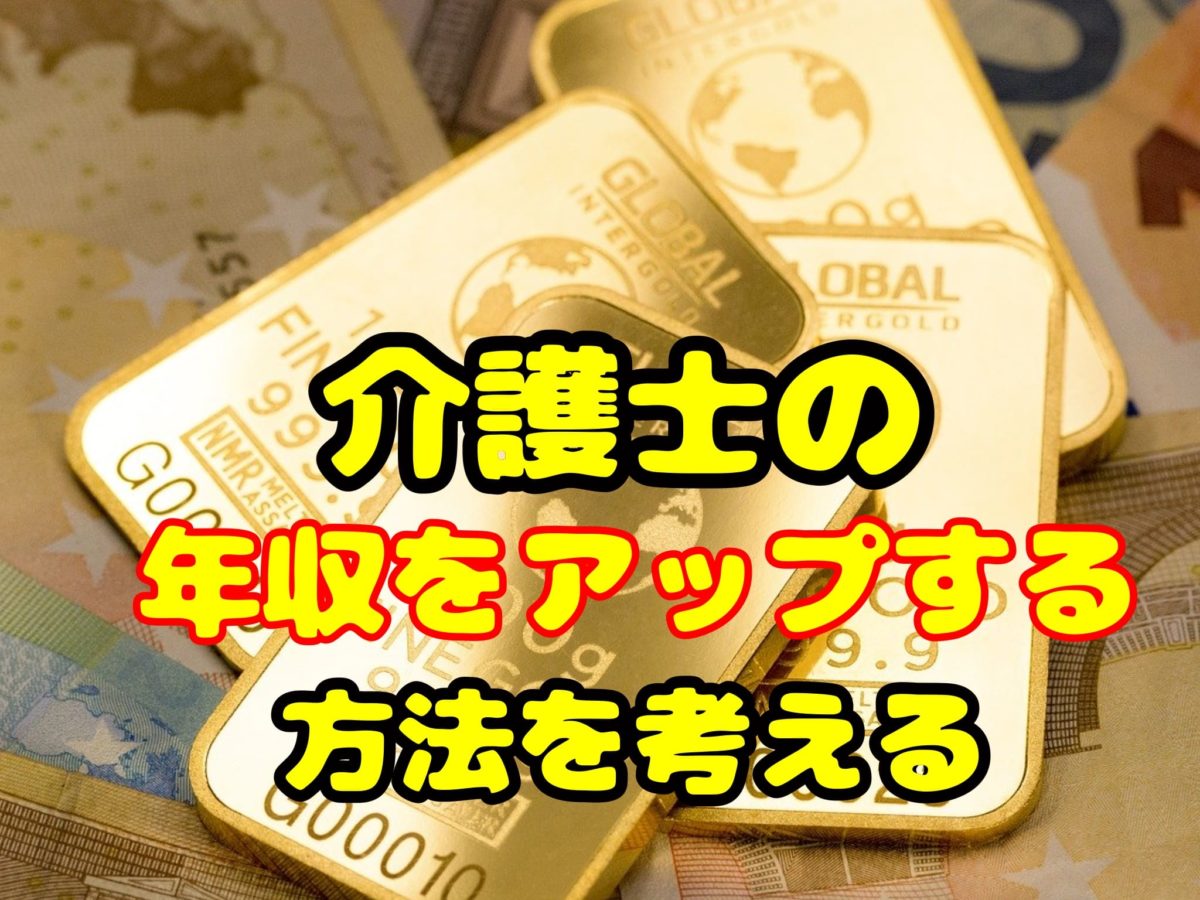
-
【5つの方法!】介護士の年収をアップする方法を考える
介護士で年収をアップさせたい!
そう思った事がある方、たくさんいますよね?
この記事では、介護士が年収を上げる為にやるべき事と、やってもあまり意味が無い事を紹介しています!
この記事を読んで、少しでも年収が上げられるように動いてみてください!続きを見る
特養の相談員がやるべきことのまとめ
特養の相談員がやるべきこと まとめ
- 相談員は入居者さん、家族、施設内の各部署の橋渡し的な業務が中心。
- 請求関係の理解、実地指導のチェック項目の理解は必須!
- 他部署とのやり取りの際は、法人や施設の考えからズレてしまっていたら、訂正しながら話し合いを進める必要がある。
- 相談員=上司 という訳では無い!えらくなったつもりで突っ走ると危険!
- 家族に対しての報告は、事故の際だけではなく、ちょっとした事もリスクを考えて、報告の必要を検討していかないといけない。
- 相談員が家族と信頼関係を作る事で、施設全体のリスク管理にもなる。
- 営業活動、見学時の上手な対応も相談員の業務にはいっている場合が多い。
- 明るい人も、そうでない人も、相談員になるのに、そこは関係ない。
相手に嫌な印象だけは与えてはいけない。
特養の相談員は、給料に比べて、プレッシャーが大きい仕事かもしれません。
しかし、介護士とはまた全然違ったスキルが身につきます。