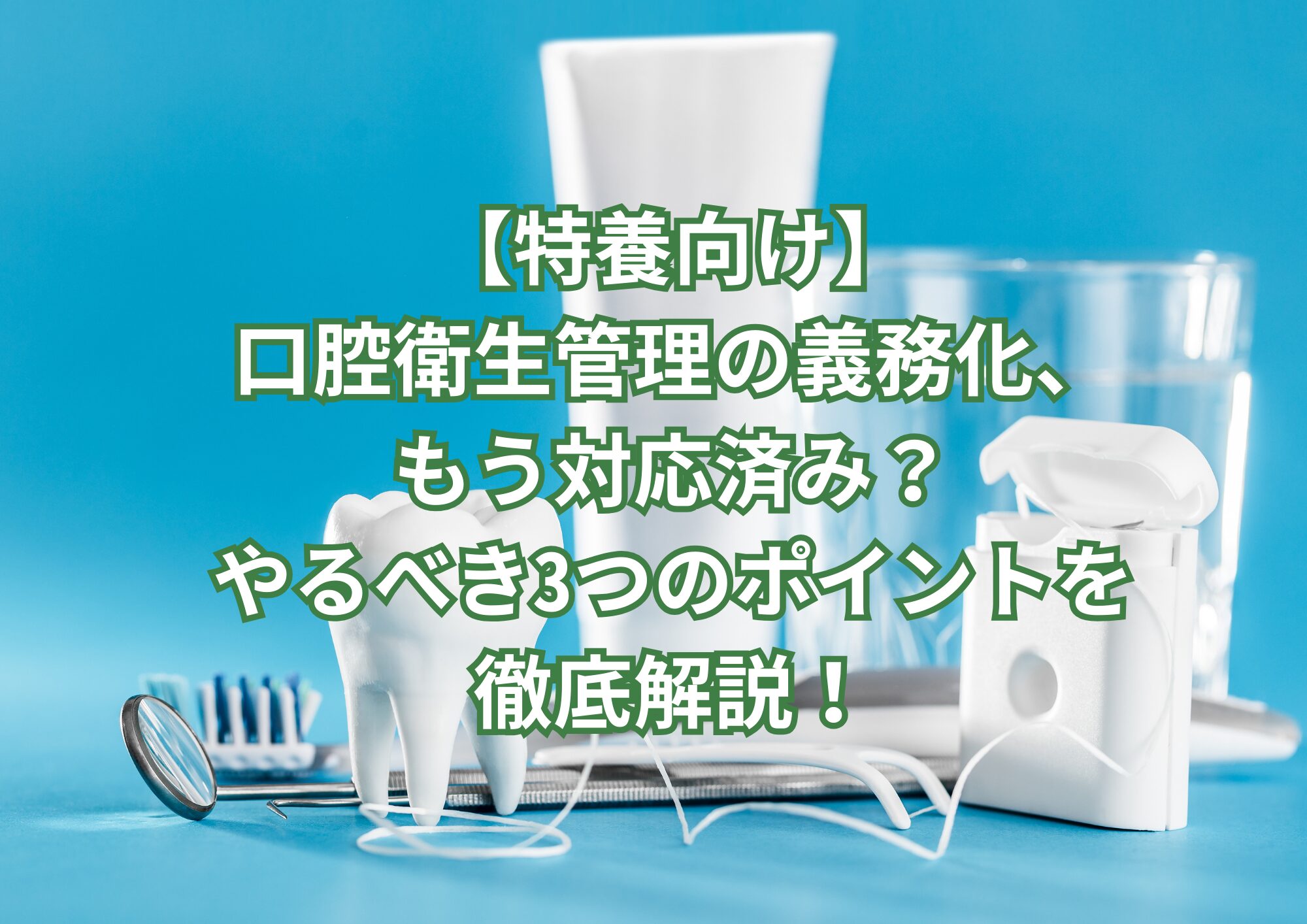内容を音声で聞く
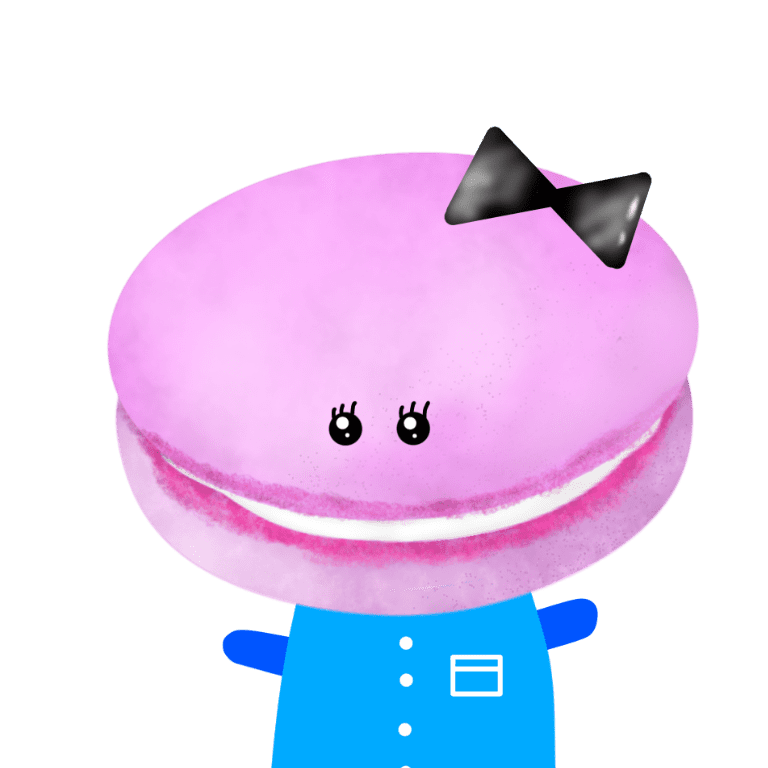
「うちの特養、口腔ケアはちゃんとやってる…はずだけど、新しい義務化って何が変わったの?」
「計画書を作らないといけないって聞いたけど、具体的にどうすれば…?」
2024年4月から、特別養護老人ホーム(特養)をはじめとする介護施設で口腔衛生管理体制の整備が義務化されました。これは、これまでの「やっていれば加算がもらえる」という任意のものから、「すべての施設が必ず実施しなければならない」基本サービスへと変わった、非常に大きな制度変更です。
この記事では、
- なぜ口腔衛生管理が義務化されたのか
- 具体的に何をすればいいのか
- 現場でスムーズに対応するためのポイント
などを、公式資料を基に分かりやすく解説します。日々の業務で忙しい現場の皆さんが、この記事を読むだけで義務化の全体像を把握し、具体的なアクションに移せるよう、要点をまとめました。
なぜ今?特養の口腔衛生管理が義務化された背景
今回の制度改正の最大のポイントは、口腔衛生管理が「特別なケア」から「当たり前の基本ケア」になった点です。
これまで「口腔衛生管理体制加算」という形で、体制を整えた施設が評価されていました。しかし、高齢者の口腔ケアが誤嚥性肺炎の予防や生活の質(QOL)の向上に直結することが科学的にも明らかになる中で、国は「一部の施設だけでなく、すべての施設で利用者の口腔の健康を守るべきだ」と方針転換しました。
つまり、口腔衛生管理は、栄養ケアや感染症対策と同じように、施設の安全と質を保つための土台として位置づけられたのです。
【結論】義務化で「やらなくてはいけない」3つのこと
忙しい方のために、まず結論から。2024年4月から特養に義務付けられたのは、主に以下の3つの体制を整備することです。
- 歯科専門職との連携:歯科医師や歯科衛生士から、施設全体に対して年に2回以上、技術的な助言や指導を受ける。
- 施設全体の計画作成:専門家の助言を基に、施設としての「口腔衛生管理体制に係る計画」を文書で作成・更新する。
- 入所者ごとの状態評価:入所者一人ひとりについて、入所時および入所後に定期的に口腔の健康状態を評価し、状態に応じた管理を計画的に行う。
(画像:歯科専門職と介護職員の連携が重要です)
いつから始まった?制度変更のタイムライン
この義務化は突然始まったわけではありません。現場が対応できるよう、3年間の準備期間が設けられていました。
- 2021年4月
- 従来の「口腔衛生管理体制加算」(月30単位)が廃止される。
- 同時に、口腔衛生管理体制の整備が「努力義務」となり、3年間の経過措置期間がスタート。
- 2024年3月31日
- 3年間の経過措置期間が終了。
- 2024年4月1日
- 口腔衛生管理体制の整備が運営基準上の「完全義務化」となる。
具体的な対応策を徹底解説!
では、義務化された3つの要件について、具体的に何をすべきか見ていきましょう。
1. 歯科専門職と連携し、年2回以上の助言を受ける
これが体制づくりの第一歩です。地域の歯科医院や歯科医師会に相談し、協力してくれる歯科医師や歯科衛生士を見つけましょう。
【ポイント】
- 目的: 個別の利用者の治療ではなく、介護職員への技術指導や施設全体の管理体制についてアドバイスをもらうことが目的です。
- 頻度: 年に2回以上、定期的に実施する必要があります。
- 形式: 施設内研修の形で実施したり、情報通信機器(ICT)を活用した遠隔での指導も認められています。
- 文書化: 誰が、いつ、どのような助言・指導を行ったか、必ず記録に残しましょう。協力関係については、書面で契約や協定書を交わしておくと安心です。
2. 「口腔衛生の管理体制に係る計画」を作成する
歯科専門職からの助言に基づき、施設全体の運営方針となる計画書を作成します。これは、個人のケアプランとは別の、施設としての戦略文書です。
【計画に盛り込むべき項目】
- 助言を行った歯科医師・歯科衛生士の氏名
- 受けた助言の要点
- 施設として達成すべき目標
- 目標達成のための具体的な方策
- 留意事項・特記事項
この計画は一度作って終わりではなく、専門家の助言を受けるたびに見直し、実態に合った「生きた計画」にしていくことが重要です。
3. 入所者ごとの口腔状態を定期的に評価する
施設全体の方針が決まったら、次に入所者一人ひとりの状態を把握します。
【ポイント】
- タイミング: 入所時と、その後も定期的に評価を行います。
- 誰が: 施設の介護職員や看護職員が実施します。
- 評価項目: 具体的には、以下のような点をチェックします。
- 開口の状態
- 歯や舌の汚れ
- 歯肉の腫れや出血
- 奥歯でしっかり噛めるか
- 食事中のむせの有無
- ぶくぶくうがいができるか
これらの評価結果を記録し、ケアプランに反映させることで、個々の利用者に合った質の高い口腔ケアを提供できるようになります。
現場の課題と成功へのカギ
制度の理想と現場の現実には、まだギャップがあるかもしれません。「協力してくれる歯医者さんが見つからない」「日々の業務に加えて、さらに記録が増えるのは大変」といった声も聞かれます。
この改革を成功させるカギは、「多職種連携」と「栄養管理との一体化」です。
口腔の問題は、食事の摂取や栄養状態と密接に繋がっています。介護職員が発見した口腔内の変化を、看護師、管理栄養士、リハビリ専門職などと迅速に共有し、チームで対応することが重要です。
例えば、食事中にむせが増えた利用者がいた場合、
- 介護職員がその変化を記録・報告。
- 看護師が口腔内のアセスメントを行う。
- 管理栄養士が食事形態の見直しを検討する。
- 歯科専門職に相談し、嚥下機能の評価や訓練について助言をもらう。
このように、口腔衛生管理をハブとして多職種が連携することで、利用者の「食べる楽しみ」を守り、誤嚥性肺炎や低栄養といった深刻な事態を防ぐことができます。これは、同じく基本サービスとなった栄養ケア・マネジメントと一体的に取り組むことで、より大きな効果を発揮します。
まとめ
2024年度から義務化された特養の口腔衛生管理は、単なる追加業務ではありません。利用者の健康と尊厳ある生活を守るための、介護の質そのものを高める取り組みです。
まずは、「年2回の専門家との連携」「施設全体の計画作成」「定期的な利用者評価」という3つの基本を押さえ、自施設の体制を見直すことから始めてみましょう。
この制度改正をきっかけに、施設全体のケアの質をもう一段階レベルアップさせていきましょう。